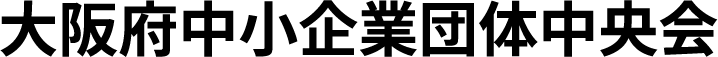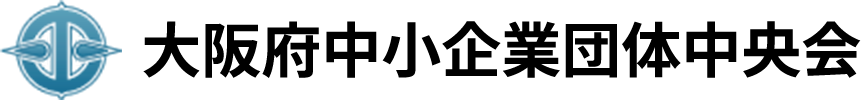1. 外国人材活用の現状と意義
- 日本の労働人口減少と中小企業の人材不足の実情
- 日本の労働人口は少子高齢化に伴い減少しており、2035年には労働力不足が深刻化すると予測されています。特に中小企業では、求人倍率の上昇、新卒者の企業への希望減少、大企業への人材流出が顕著で、人手不足が喫緊の経営課題となっています。これにより、中小企業は人手不足倒産の増加、事業縮小、労働環境の悪化など、事業継続への危機感を募らせています。
- 外国人労働者数の推移や活用状況
- 日本の外国人労働者数は2024年10月末時点で約230万人に達し、過去最高を更新しました。これは少子高齢化による労働力不足が深刻化する中で、人手不足の解消と経済成長への貢献が期待されており、今後も増加が続くと見込まれています。多様な在留資格制度が整備され、専門的・技術分野や技能実習制度、そして「特定技能」などの活用が進んでいます。特に人手不足が深刻な製造業、建設業、介護・福祉分野などで受け入れが進んでおり、外国人労働者は日本の産業を下支えする重要な存在となっています。
- 外国人材活用のメリット
- 外国人材活用には、人手不足解消や若くて優秀な人材の確保、社内活性化や新たなアイデアの創出、海外展開の足がかりとなるなど、多くのメリットがあります。また、訪日外国人への多言語対応力向上や、助成金・補助金の活用、企業イメージ向上にもつながります。
- 参考 内閣府 中小企業庁
2. 採用の仕組みと制度
- 主な在留資格(特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務等)の概要
- 「特定技能」について:「特定技能」とは、人手不足が深刻な特定の産業分野で、日本で働くことを目指す外国人向けの新たな在留資格です。2019年に創設され、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。1号は相当程度の知識・経験、2号は熟練した専門的な技能が必要で、在留期間や支援義務の有無などが異なります。
- 技能実習について:「技能実習」とは、日本が国際貢献の一環として、開発途上国の外国人を受け入れ、日本の優れた技術・技能・知識を移転する制度でしたが、本来の趣旨と人手不足解消という現実との乖離や、労働環境の問題が指摘されてきました。この制度は2024年に廃止が決定され、2027年までに新しい「育成就労制度」に移行する予定です。
- 「技術・人文知識・国際業務」について:「技術・人文知識・国際業務」とは、自然科学・人文科学の専門知識や技術、あるいは外国の文化に根差した思考・感受性を必要とする業務に従事する外国人が日本で働くために取得する「在留資格(ビザ)」のことです。システムエンジニアや通訳、デザイナーなどが代表的な例であり、一般的に「技人国(ぎじんこく)」と略されます。これは「高度な専門知識や技術を日本に活かすこと」を目的とした就労ビザの一種です。
- 参考 特定技能 技能実習 技術・人文知識・国際業務
3. 定着・活躍のための環境づくり
- コミュニケーション支援(やさしい日本語、社内研修)
- コミュニケーション支援として、やさしい日本語の学習、翻訳ツールの活用、そして社内研修が効果的です。やさしい日本語は、外国人だけでなく高齢者や子どもなど、日本語の理解に困難を抱える人全般を対象とした配慮ある日本語表現で、平易な言葉遣いや単純な文法構造が特徴です。コミュニケーションを円滑にするために、これらの方法を組み合わせて実践することが重要です。
- 職場環境整備(相談窓口、文化・宗教・食習慣への配慮)
- 外国人材を受け入れる際には、相談窓口を設置し、文化・宗教・食習慣への配慮が重要です。相談窓口では、異文化理解を深め、コミュニケーションを円滑にするための情報提供や多言語対応を行います。文化・宗教面では、断食月中のイスラム教徒への業務調整、礼拝場所の確保、食習慣への配慮としてハラル対応の食堂や食材の準備などが求められます。
- 長期的な定着と成長のために
- 日本語教育、キャリア形成支援、働き方改善は、外国人労働者の長期的な定着と成長に不可欠な要素です。専門的な日本語教育を受けることで、円滑な業務遂行と職場環境への適応を促し、キャリア形成支援は個々のスキルアップとキャリアパスの明確化を支援します。さらに、働き方改善によってワークライフバランスを向上させることは、モチベーションの維持や心身の健康を保つ上で重要であり、これらが相乗効果を生むことで、外国人労働者は持続的に働き続け、組織の活性化にも貢献できるようになります。
- 参考 総務省 法務省 文化庁
4. 成功事例と導入に際して
- 中小企業の外国人材受入の実際
- 外国人材受け入れに成功した事業所の中には、人手不足解消を背景に、専門知識を持つ特定の国籍の労働者を技術や文化の違いを乗り越えて受け入れ、企業文化との適合、キャリアパスの提供、そして多文化共生への意識改革が鍵となったケースがあります。例えば、特定の技術を持つ東南アジア出身の技能実習生を受け入れ、社内語学研修と外国人社員の活躍を支援する組織体制を構築し、労働環境の整備と公正な待遇により、生産性向上と新規顧客獲得に繋がった事例などがあります。
- 参考 経済産業省
- 外国人労働者の導入に際して
- 外国人労働者を導入する際には、在留資格の確認、業務内容との適合性確認、日本語能力の把握、採用前の必要書類の準備、入社後のハローワークへの届出義務確認など必要です。在留資格や就労許可の有無を確認し、職種に合った日本語能力を持つ人材を選考することが重要です。また、入社後には速やかにハローワークへ届け出る義務があるため、手続きも漏れなく行いましょう。
- 参考 厚生労働省
外部リンク
法務省 出入国在留管理庁
厚生労働省
大阪労働局
経済産業省
外国人技能実習機構
JITCO(国際人材協力機構)